神経を抜いた歯が痛い原因とは?その治療法を紹介
Contents
重症化した虫歯では、歯の神経を抜く「抜髄(ばつずい)」が行われます。細菌に感染した歯の神経は保存することが難しいことに加え、そのまま放置すると歯痛がどんどんと強まっていってしまうからです。けれども、症例によっては神経を抜いた歯が再び痛くなることもあります。神経が存在していないのになぜ痛むのか、不思議に思われていることでしょう。ここではそんな神経を抜いた歯が痛い原因や治療法について、わかりやすく解説します。
神経を抜いた歯が痛くなる場合の症状

神経を抜いた歯が痛い、といってもその症状はケースによって少し異なります。抜髄後の痛みに悩まされている方は、どの症状に当てはまるかチェックしてみてください。
症状①食事すると痛い
食事の際、食べ物を噛んだ時に歯やその周囲に痛みを感じることがあります。一般的な虫歯は、安静時にもジンジンと痛むので、症状が少し異なるのはおわかりいただけるかと思います。噛んだ時の痛みも違和感程度にとどまる場合や鋭い痛みが走る場合など、個々人で大きく変わってきます。
症状②歯茎の腫れ
神経を抜いた歯の周囲の歯茎に腫れが認められることがあります。歯茎そのものに痛みを感じることもあれば、口内炎のような膨らみがあったり、違和感が生じていたりすることもあります。これも症状はケースによってバリエーションがあります。
症状③歯に違和感がある
強い痛みは感じないけれど、歯に違和感がある場合も何らかの異常が疑われます。歯の神経は抜いているはずなのに違和感・不快感が生じるのであれば、一度歯科医院で検査を受けましょう。
神経を抜いた歯に痛みが出る原因
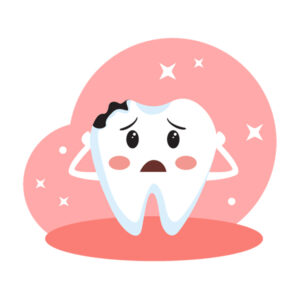
神経を抜いたにもかかわらず、歯痛や歯茎の違和感・不快感などが生じるのであれば、次に挙げるような原因が考えられます。
原因①歯が割れている
噛んだ時に歯に鋭い痛みが生じる場合は、歯根破折(しこんはせつ)が疑われます。外傷などで歯に強い力が加わったり、神経を抜いた後に設置した土台によって、歯根に過剰な負担がかかったりした場合に起こる症状です。歯の割れ方によもよりますが、基本的には抜歯が適応されます。そのまま放置すると歯茎や歯槽骨に炎症を引き起こし、病態のさらなる悪化を招いてしまいます。
原因②噛み合わせが合っていない
嚙み合わせが合っていないと、神経を抜いた歯でも痛みが生じることがあります。これは嚙み合わせの異常によって、治療した歯に過剰な負担がかかり、歯根膜などの歯周組織に刺激が加わるためです。歯そのものが痛いのではなく、歯の根っこの先や歯周組織の部分で痛みを感じています。
原因③歯周病が進行している
神経を抜いた歯は、虫歯による歯痛が生じることはありませんが、歯周病による痛みは発生します。虫歯治療後も歯や歯周の衛生状態が悪い場合は、歯周病を進行させてしまいます。その結果、歯茎に炎症が起こって痛みや腫れなどの症状を引き起こすのです。虫歯による痛みとはかなり種類が異なるものなので、比較的判別しやすいことかと思います。
原因④根管治療(神経の治療)が不十分
歯の神経を抜く抜髄処置のあとには、歯の根っこの内部をきれいにお掃除する根管治療が必要となります。根管内をリーマーやファイルといった器具を使って形成・清掃し、薬剤を用いて消毒・殺菌します。そうした根管処置が不十分だと、残存した細菌が再び活動を始め、炎症反応などを引き起こすようになります。これもまた神経を抜いた歯が痛む主な原因のひとつといえます。根管治療はもともと難易度の高く、保険診療での成功率は50%程度といわれています。そのため、根管治療が不十分で歯の痛みが生じたとしても、頑張ってもう一度、歯の根の中をきれいにお掃除しましょう。
原因⑤歯の根の中に膿が溜まっている
歯の根の中に膿が溜まっている場合も、歯に痛みを感じることがあります。歯根内に病変が残っているのですから、痛みが生じて当然といえば当然ですよね。ただし、痛みを感知しているのは歯の神経ではなく、歯根膜などの歯周組織です。もちろん、歯の神経の取り残しがある場合は、通常の歯痛が生じます。いずれにせよ、根管内をきれいにお掃除する処置が必須となります。
ちなみに、歯の根の中の膿をそのまま放置すると、根尖孔(こんせんこう)と呼ばれる歯の根っこの先の穴からが細菌などが漏れ出て、根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)という病気を発症します。これもまた神経が死んだ歯の痛みにつながるため要注意です。
神経を抜いた歯が痛い場合の治療法

神経を抜いた歯が痛い場合の治療法には、いくつかの選択肢があります。
治療法歯周病治療
抜髄後の痛みが歯周病に由来している場合は、当然ですが歯周病治療が必要となります。歯周組織に痛みや腫れ、膿の塊が形成されている時点で、かなり進行していることが予想されるため、歯周基本治療のみで改善することは困難と思われます。歯茎をメスで切開し、歯根面の歯石を取り除くなどの歯周外科治療も行うことになるでしょう。
治療法抜歯処置
歯根が割れていたり、精密根管治療でも症状の改善が見込めなかったりする場合は、抜歯処置を施すことになります。歯根破折では、ほとんどのケースで歯を抜くことになる点にご注意ください。とくに歯根が垂直的に割れている場合は、手の施しようがないため、抜歯を余儀なくされます。根管治療に関しては、歯を保存するための最後のとりでともいえるものなので、時間が長くかかったとしても、最後まで頑張ってやり切りましょう。その結果、抜歯を選択せざるを得なくなるケースも多々あるのが現実です。















